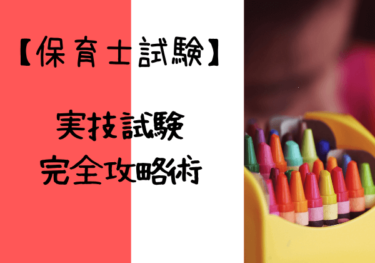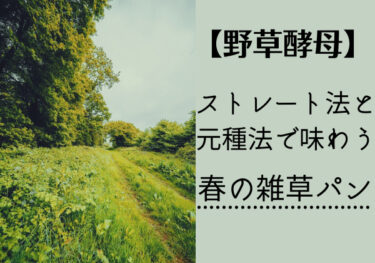みなさん、こんにちは!シジミです。
今年も梅の季節がやってきました。
毎年近くの農園に出向き、子どもたちと一緒に梅もぎをしています。
梅を使った保存食は、とっても美味しくて、作り方も簡単なものばかりなので、ぜひ作ってみてくださいね!
毎日変化していく梅のビンを見ながら、出来上がりを楽しみに過ごすのも良いものですよ^^
梅仕事って何?
6月前後になると、直売所やスーパーに一斉に並び出す青梅。
生梅の状態ではすぐに傷んでしまいますが、梅干しや梅酒などの保存食品として加工することで、長期にわたって美味しくいただけます。
「旬の時期に、季節を感じながら梅の保存食を作ること」=「梅仕事」と呼ばれているのです。
梅の効果効能
梅には、クエン酸、リンゴ酸、コハク酸、酒石酸など、様々な有機酸が含まれています。
これらの有機酸は、疲労回復、殺菌作用、動脈硬化や脂肪燃焼にも効果があると言われています。
また、夏バテで食欲がないとき、妊娠中のつわり時期にも、酸味のある梅はさっぱりと食べることができますよね。
梅は多くの果物の中でも、栄養価が優れていて、タンパク質、ビタミンE、カルシウム、カリウム、リン、鉄などのミネラル分も豊富に含んでいます。
伝統食材として身近に親しまれていますが、日本の先人は良いところに目をつけたなぁと、一子孫として思います。
梅で作る保存食のレシピ
梅ジュース(梅シロップ)
水、炭酸、お湯で割って梅ジュース、かき氷のシロップに、ゼリーにしたり・・・と無限に使える梅ジュース。
甘酸っぱくて、懐かしいこの味、毎年作っています♪
<材料> 果実ビン4L使用
- 青梅・・・1kg
- 氷砂糖・・・1kg
- ホワイトリカー・・・適量

ヘタを取り除く 
水洗い後、ホワイトリカーで表面を消毒 
氷砂糖と梅を交互にビンに詰める 
1週間後、まだ氷砂糖が少し残っている
うすめじゅーうのうめやちん(笑)
「うめじゅーすのうめちゃん」だそうです。by5歳の娘
- 梅のヘタを爪楊枝などで取り除く。
- 梅を水で洗い、ザルで水を切り、ボウルに移す。
- フォークで梅に何か所か穴を空ける。
- ホワイトリカーをボウルに適量入れて、梅を転がす。
- 消毒した果実ビンに氷砂糖と梅を交互に入れ、冷暗所で保管する。
- 2~3日後、氷砂糖が解けてきたらビンをゆすり、梅のエキスの抽出を助ける。
氷砂糖が全て溶けきったら出来上がり。
梅干し
梅仕事の定番と言えばこれですね!
これまでは重石をして作っていたのですが、重石なしにしてみたところ、柔らかくてジューシーな梅干しが出来上がりました♪
料理にも使いやすく、子どもたちにも好評だったので重石なし採用です^^
今回は青梅を収穫したため、追熟させました。
既に熟した黄梅を使用する場合は、追熟工程は読み飛ばしてくださいね♪
追熟の方法
青梅をザルに広げ、2~3日冷暗所に置きます。
今回はこのやり方で追熟させましたが、しわが寄り始めたり、乾燥していきそうな気配だったので、2日目で回収しました。
その後は熱湯をかけて強制追熟させました。
👇こちらのレシピを参考にさせていただきました!
母が40年以上作り続ける「お湯をかける」漬け方です。柔らかい梅干が好きな方、手軽に漬けたい方に!焼酎も重石も使いません!…
強制追熟の方法
- 梅のヘタを爪楊枝などで取り除く。
- 梅を水で洗い、ザルに取る。
- やかんいっぱいに熱湯を沸かし、ザルの下にボールを当てた状態で、熱湯を注ぐ。
- 20秒間梅を熱湯に浸す。※湯だって皮が破れやすくなるので20秒より長くは浸さない
- お湯をきり、荒熱をとる。

強制追熟前 
強制追熟後
熱湯から上げた直後は、もう少しかな?という感じでしたが、ザルでお湯切りをしている間にみるみる黄色くなりました!
これはすごい!!
今まで数日間かけて行う追熟が上手くいかなかった人は、ぜひ試してみてください^^
梅干しの作り方
<材料> 果実ビン4L容量
- 青梅・・・1㎏
※熟した黄梅でももちろんOK!すぐに使えます! - 粗塩・・・梅重量の15%(150g)

梅半量を入れる 
塩を1/4まぶす 
梅酢が上がった状態(3日後)
- 追熟させ、荒熱を取った梅の半量を消毒したビンに入れ、塩を上から1/4量まぶす。
- 残りの梅を入れ、残りの塩をまぶす。
- 重石はせずに、一晩放置すると少しずつ梅酢が上がる。
- 梅酢が上がり始めたら1日に数回ビンを傾けて、梅全体に梅酢をなじませる。
- 白梅干しの場合はこのまま漬けて置き、梅雨が明けてから3日間連続で晴天になる日を選び、梅はザルの上に広げて日当たりの良い場所で天日干しする。できれば途中で、梅を上下ひっくり返す(※土用干し)
夜間は室内でも良いが、風通しの良い場所で保管する。翌朝また天日干しをする。(合計3日を目安に)
梅酢もビンの口にラップをして、一緒に天日干しし、日光消毒する。 - 梅を梅酢に戻し、冷暗所に保管。(3カ月ほど置くと味がよりなじむ)
★天候がいまいちになってしまったとき★
- 曇天、日当たり良好の場所がないとき
⇒梅を乾燥させることが一番の目的なので、風通しの良い場所で干す
場合によっては3日以上乾燥させた方が良い - 「晴天→雨天→雨天」に天気予報が変わってしまったとき
⇒梅を再度梅酢に戻して、晴天が続く日を狙って再チャレンジ - 急な雨で梅が少しだけ濡れてしまった
⇒ホワイトリカーをしみこませたキッチンペーパー水分をふき取り、自然乾燥させる
後は通常通りの作業でOK - 急な雨で梅がガッツリ濡れてしまった
⇒キッチンペーパーで水分をふき取り、ホワイトリカーにくぐらせた後、再度キッチンペーパーでふき取る。
もう一度梅酢に戻して、晴天が続く日を狙って再チャレンジ
<赤紫蘇を漬け込むー下処理方法>
白梅干しにする場合はこの工程は省いてくださいね!
我が家は「自家製ゆかり」を作りたいので、毎年多めに赤紫蘇を漬け込んでいます♪
<材料>
- 赤紫蘇・・・200g(梅の量の10~20%が目安)
- 粗塩・・・36g(赤紫蘇の18%目安)
- 仕込んだ梅から上がってきている梅酢・・・200㎖

赤紫蘇の葉のみを取り、洗う 
何かの卵発見!! 
1回目塩もみ 
2回目塩もみ 
梅酢を加える 
左:梅酢投入前 右:梅酢投入後 
梅ビンに紫蘇と梅酢を投入
- 赤紫蘇の葉のみを取り、水でよく洗って水分をザルで切る。
- ボウルに紫蘇の葉と粗塩半量を加え、パンをこねるようにしっかりと塩もみする。(5分くらい)
- きつく絞り、濃い紫色の汁=アクを捨てる。
- 再度ボウルに絞った紫蘇を入れ、残りの粗塩を加え、しっかりと塩もみする。(5分くらい)
- きつく絞り、アクを捨てる。
- 絞った紫蘇に梅酢を200㎖加え、菜ばしでほぐすようになじませる。(紫色から赤色に変化!)
- 梅のビンに6.の紫蘇と梅酢を合わせ、梅の上部を覆うように紫蘇をかぶせる。
紫蘇の色を梅に移すように、1日数回ゆすってなじませる。 - 土用干し(※上記参照)を行い、梅を梅酢に戻して冷暗所に保管する。(3カ月ほど置くと、味がよりなじんで美味しい!!)
土用干しの後、我が家では梅酢に再度梅を戻して保管しています。
ふっくら柔らかくいただけますよ♪
発見した卵の正体・・・
赤紫蘇を仕込む際に発見した卵の正体が気になり、子どもたちと虫かごの中に入れて観察していました。
2日後、卵がついに孵化しました!!

きれいな蝶々の幼虫が出てくることを期待していましたが、残念!!
クサギカメムシの卵でした~😨
この時期旬の大葉(青じそ)のレシピも紹介しています♪
今年もシソの季節がやってきましたね! 和風でも洋風でも、どんな料理にもちょい足しするだけで一気に美味しくしてくれるシソ♪ 和製ハーブとも言われますが、こんなにオールマイティに使えるハーブもなかなかありませんね。 地植えす[…]
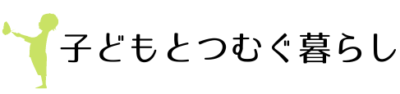


















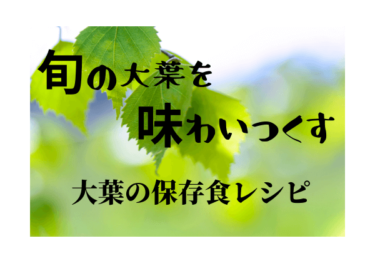
![【保育士試験】[長文暗記]保育所保育指針を暗記する方法](https://kototsumugu.com/wp-content/uploads/2021/06/13379744e5453d2e6a5f8f7d737073ac-375x263.png)