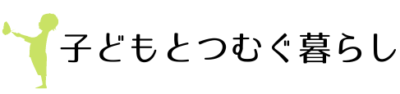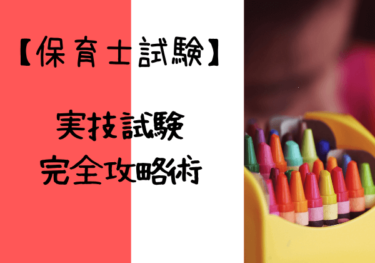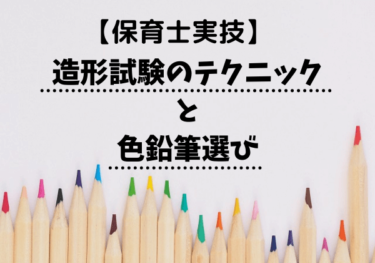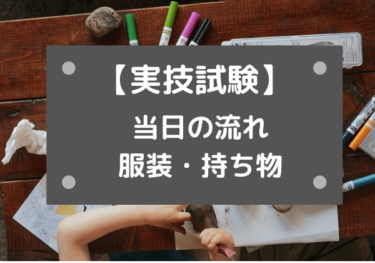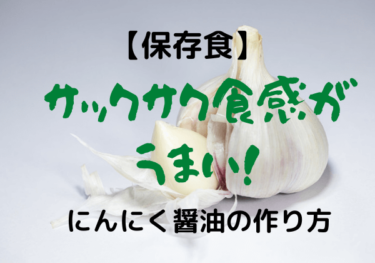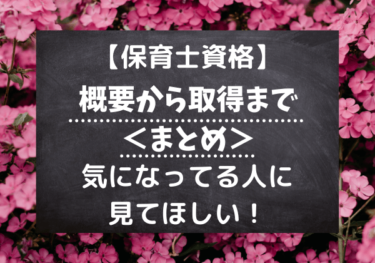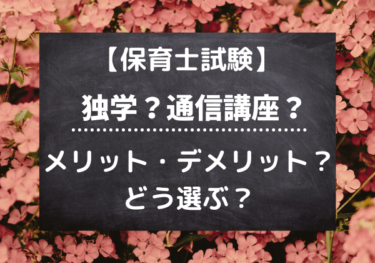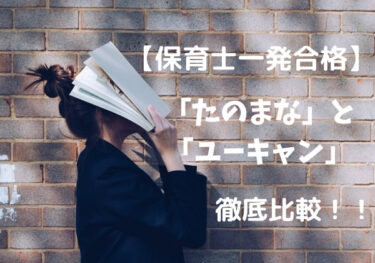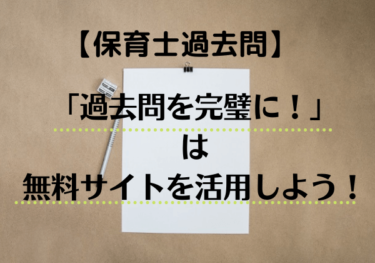保育士試験の実技試験はみんな受かるから、対策は必要ない!?
いえいえ、そんなことはありませんよ!!
逆に実技試験を落とすなんて、そんな勿体ないことはありません!
たしかに筆記試験と比較すると、合格率が高いのも事実ですが、実技試験には実技試験特有の難しさがあるのです。
テクニックをしっかり習得して、最後まで頑張りましょうね^^
選択科目の選び方
実技試験には下記の3分野があり、この中より2分野を選択して実施します。
筆記試験同様、6割以上の得点で合格となります。
ちなみに実技試験はそれぞれ50点満点なので、2分野ともに30点以上で合格です。
- 音楽に関する技術
- 造形に関する技術
- 言語に関する技術
さて、当たり前ですが、一番良いのは得意分野を二つ選択することです。
ただし、「音楽に関する技術」を選択する場合、ピアノ、ギター、アコーディオンのいずれかの楽器を選んで演奏することになります。
そのため、これらの楽器を練習する環境が必要になります。
ちなみに私はピアノは弾けますが、自宅に楽器がなく、他に練習できる環境もなかったため、「造形に関する技術」と「言語に関する技術」で受験しています。
なので、「音楽に関する技術」を選択されるみなさん、大変申し訳ないのですが私からは試験対策やその他詳細をお伝えすることができませんので、ご了承いただければと思いますm(__)m
実技試験のポイントとは?
実技試験特有の難しさとは、一体何でしょうか?
- 試験官の前でパフォーマンスするのはものすごく緊張する
- 時間制限が伴うため、とにかく焦る
そう、実技試験最大の敵は緊張と焦りです。
「造形に関する技術」は、時間と焦りとの闘いです。
「言語に関する技術」では、試験官の視線にも緊張しますし、会場にもよるかもしれませんが、前の受験者の声が丸聞こえです。
そして、実技対策をついついおろそかにしてしまう油断が、緊張と焦りをより生み出してしまうのです。
したがって、実技試験の緊張と焦りを克服するポイントは、とにかく練習して試験慣れをしておくことです!
「造形に関する技術」の試験対策
「造形に関する技術」試験概要
試験当日に提示された問題文と条件の絵を、45分間で縦横19㎝の枠内に描く。
鉛筆又はシャープペンシル(HB~2B)、色鉛筆(12~24色程度)、消しゴム、腕時計の4点が机上に持ち込み可。
携帯用鉛筆削りも会場内に持ち込み可だが、試験監督員の了解を得てから使用すること。求められる力:保育の状況をイメージした造形表現(情景・人物の描写や色使いなど)ができること
<試験対策の流れ>
- 色鉛筆をそろえる
12~24色の色鉛筆をそろえます。
100円ショップや何かの景品のような色鉛筆だと、色が薄かったり、芯が折れやすいことがあります。
保育士になってからも使う機会は出てくると思うので、これを機に1つきちんとした色鉛筆を持っておくと良いと思います。
ポイント
試験当日に水の使用は不可ですが、水彩タイプの色鉛筆は発色がよく、芯が適度に柔らかいため塗りやすくおすすめです。
輪郭線でよく使用する茶色などは、差支えなければ両端削り(貧乏削り)をおすすめします^^
試験中は鉛筆削りの使用に試験監督員の許可が必要になるため、タイムロスになるからです。
色鉛筆、みなさん持っていますか? 子どもから大人まで、色塗りと言えば「色鉛筆!」というほどおなじみの文房具ですね。 趣味の絵なら、色鉛筆なんて何でも良いか~とも思います。 でも、造形試験ではどんな色鉛筆が良いのか、色鉛筆[…]
- 場所(園庭、園舎、公園など)が想定できるアイテムをあらかじめ決め、描く練習をする
「造形に関する技術」で出題される問題は、「保育の状況をイメージできる場所」とあるので、だいたい園庭、園舎、公園などの場所が指定されます。
したがって、一目見てその場所とわかるアイテムを背景に描き入れると良いです。
そして、あらかじめそのアイテムを決めて、描く練習をしておくと時間短縮になります。
【例】
園庭:奥に見える園舎
園舎:子ども用のイス、壁に貼られた制作物
公園:ブランコ、すべり台などの遊具
ポイント
園舎や園庭は、普段入る機会がないとなかなか想像できないかもしれません。
あらかじめ、写真をネット検索してみたり、幼稚園・保育園の情報誌やHPなどを見ておくとイメージがわきやすいです。
- 人物の描き方
人物については、うまい下手は当然あるのですが、「人間」を描きましょう。
棒人間や、手がアンパンマンのように指なし、関節の数が多かったり少なかったりはNGですよ!
最初は特に、動きのある人物を描くのは難しいと感じるかもしれません。
まずは、あとで消せるように鉛筆で薄く、下書きを描き入れていきます。
〇などの図形を使い、関節部分ごとに区切ると、動きの形がとりやすいです。
顔は、縦横に十字のマークを入れ、真ん中より少し下の部分に鼻を描き入れると、向きが出やすくなります。
体の動きや顔の向きが決まったら、茶色の色鉛筆で輪郭線を入れていきます。
先ほどの鉛筆の下書きに、手の指や顔のパーツ、服などを肉付けするイメージで描き入れていきましょう!

向かって左の女の子の顔パーツは黒、男の子の顔パーツは茶色で描いてみました。
黒はダメではありませんが、鉛筆の黒と違って、色鉛筆の黒は濃く出やすいため、浮いた感じになりやすいです。
茶色の方が全体的に明るく柔らかい印象かと思います。
他の色ともなじみが良いので、顔のパーツや輪郭線には茶色使用するのをおすすめします!
ここからは実際の過去問をもとに説明していきます。
<問題>
【事例】を読み、次の4つの条件をすべて満たして、解答用紙の枠内に絵画で表現しなさい。
【事例】
雨上がり、K保育園の園庭にいくつか水たまりができました。
長ぐつをはいた子どもたちが水たまりにジャブジャブ入ったり、
葉っぱを浮かべたりしながら楽しんでいます。
その様子を見て、保育士が声かけをしています。
【条件】
1 水たまりで遊んでいる子ども達および保育士を描くこと。
2 園庭の様子がわかるように表現すること。
3 子ども3名以上、保育士1名以上および水たまりを表現すること。
4 色鉛筆で色をつけること
まずは、何を描き入れなくてはいけないのかを整理します。
- 保育園の園庭、水たまり
⇒奥に園舎を描き入れる
⇒水たまりを描き入れる - 子ども3名以上、保育士1名以上
⇒とりあえず子ども3名、保育士1名を描き、余裕があれば増員 - 事例、条件に合った人物を描く
⇒長ぐつをはいた子どもたち
⇒水たまりに入っている子
⇒葉っぱを浮かべている子
⇒声かけをしている保育士
次に、答案用紙と同じ19㎝四方の枠を紙に描き、それぞれの位置を決め、アバウトでいいのでマークします。
- 園舎、水たまりの位置
- 子ども、保育士の位置
私もこういう感じの絵は得意ではありません^^;
お手本と言うにはおこがましいので、作品例だと思ってください。
腕の動きとか不自然・・・難しいですよね^^;

園舎、水たまり、子ども3名、保育士1名の位置が決まったら、鉛筆で下書きを描きます。
園庭には遊具があるため、遊具を描きこむのも良いと思います。
ただ、公園なのか園庭なのかというところをよりはっきり区別するために、園舎を描き入れることにしました。
園舎はただの建物だと何か良くわからないので、てるてる坊主や、色紙で作った輪飾りを入れてみました。

茶色の色鉛筆で輪郭線を入れました。
鉛筆の下絵は消しゴムで消します。
消しゴムはこすると汚れが出てしまうので、トントンと軽く叩くように使うと鉛筆の線がきれいに落とせます。
色鉛筆で描き損じていますね~^^;
こういう場合は、焦らず濃いめ色の洋服にしたり、背景色でごまかすと良いです。

最後に色塗りをします。
斜線が目立つような雑な塗り方ではなく、なるべく丁寧に塗ります。
濃いめに塗ると、立体的に、全体の印象も明るく見えます。
時間の限り色塗りをして、フリーハンドで遊具や園舎の中のイスなども描き入れました。
45分間という時間は、思ったよりもずっと短く感じると思います。
描きなれておくことで、時間配分を意識しながら試験を受けることができるので、過去問を利用して10枚くらいは描いておくとコツをつかめると思います。
「言語に関する技術」の試験対策
「言語に関する技術」試験概要
3歳児クラスの子ども15人程度に向けて、3分間のお話を想定。
課題のうち1つを選択し、子どもが集中して聞けるように身振りや手振りを交えてお話をする。
絵本、台本、その他小道具類の持ち込みは禁止。求められる力:保育士として必要な基本的な声の出し方、表現上の技術、幼児に対する話し方ができること。
<試験対策の流れ>
- 台本の作成
課題の中から1つの物語を選択し、絵本などを参考に3分以内になるよう、話をまとめます。
ポイント
実際にやってみるとわかるのですが、絵本の内容を3分にまとめるのは結構大変です。
落語のように、セリフをメインで組み立てると良いです。
- 台本を暗唱する
何度も繰り返し音読して暗唱します。
途中で止まったり、思い出すのに時間をかけると、3分以内に組み立てた台本が終わらなくなるので、しっかり覚えましょうね。
ポイント
ここで注意したいのが、早口にならないようにすることです!
幼児にわかりやすく話すことが大切なので、余裕のある、落ち着いたペースをつかみます。
もし台本の内容が3分を超えてしまうようであれば、ここで修正します。
- 鏡の前で練習する
鏡の前でお話の練習をします。
自分に見られているだけなのに、頭が真っ白になりますが、何度も落ち着いて練習を繰り返しましょう!
ポイント
目線、表情、身振り、手振り、声の抑揚を意識して、練習します。
- 人前で話す練習をする
家族、友人、子どもでも誰でも良いです。
恥ずかしがらず、誰かにお話しの練習相手になってもらいます。
ポイント
相手の顔をしっかり見て、身振り・手振りをつけつつ、いきいきとお話をしてください。
当日は椅子を子どもに見立ててお話をすることになります。
目線は気持ち上にもっていった方が、声も響いて表情が明るく見えます。
お話は早すぎず、遅すぎず、3分程度になるように仕上げていきます。
- 話だけではなく、入退室についてもきちんと練習し、イメージをつかんでおきましょう!
面接なんて久しぶり!という方も多いと思います。
今一度、ドアの開け方や挨拶、礼儀作法など確認しておくと、試験に集中できますよ^^
まとめ
実技試験の選択をするときは、「練習する環境があるか」をまず考えましょう!
全く練習せずに挑んでしまうと、ある意味筆記試験よりどうにもなりません^^;
泣いて逃げたくなります・・・油断せずに対策しましょうね!
造形に関する技術
- 時間内に条件を厳守した絵を描き上げる
- 明るい色味、雰囲気で
- 45分間最後まで色塗りを怠らない
言語に関する技術
- 大きな声で、表情豊かにいきいきと話す
- 噛んだり間違えても、堂々と明るく
- 早口にならないように落ち着いて話す
たくさん練習したから大丈夫!
自分を信じて、最後まで明るく頑張りましょうね^^
いよいよ実技試験ですね! 実技試験は緊張との戦いですが、合格率は筆記試験と比較してかなり高いです! 自信を持って、最後まで頑張りましょうね^^ 実技試験当日のスケジュール 実技試験は、「造形に関する[…]