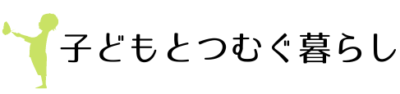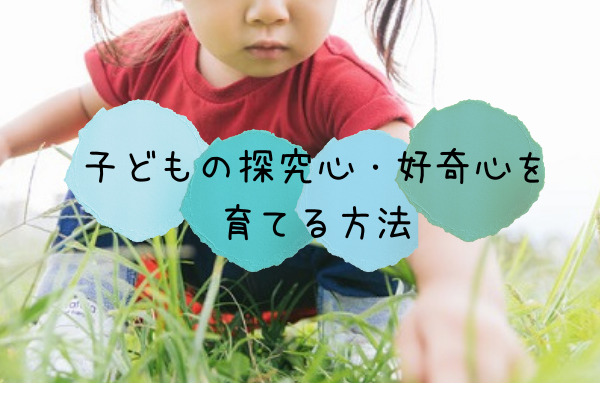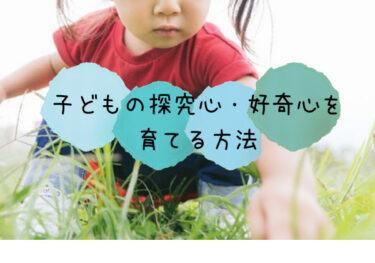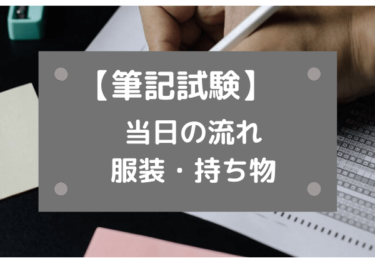我が家ではペットを飼っています。
ペットと言ってもワンちゃん、ネコちゃんではなく、もっぱら水生生物です。
熱帯魚のベタの水槽、レモンテトラとシノドンティス・ペトリコラの混泳水槽、アカヒレの水槽、屋外飼育でミユキメダカなどを飼育しています。
特に珍しいお魚さんはおらず、皆わりとリーズナブルで、飼いやすいものばかりです。
お魚の良いところは、ズボラな飼い主でも許してくれるところでしょうか!?
- 2週間くらいエサがなくても生きている
- 散歩の必要なし
- 臭いは水が封じ込めてくれる
- 相当藻が生えても生きている
- エサ代、維持費が激安
- 産卵して、次世代の成長を見せてくれる
なんてことを友人たちに話すと、「生き物に詳しいよね」「色々なことを知っているよね」と言ってくれるのです。
でも実際、飼っている人たちからすると、何てことはない知識ですよね^^
そもそもなぜ興味が持てるのか

私が生き物に詳しいのかはさて置き、いつも言われるのが、
「なぜそんなに興味が持てるのか」
「虫とか気持ち悪くないのか」
「なぜそんな風に育ったのか」
といったことなのですが、特に特殊な幼少期を過ごしたとは思っていません。
わりと続けていた習い事もピアノくらいで、むしろそんなに教育熱心な両親でもないような・・・。
自分でもなぜだろう?と思い返して、1つ思い当たったことがありました。
常に図鑑があった
本棚の一番下、子どもでも取れる位置に、図鑑があったのです。
絵本より図鑑を読んでいたことを思い出しました。
植物図鑑、恐竜図鑑、宇宙図鑑、昆虫図鑑、動物図鑑、そして小学校3年生くらいの誕生日に人体図鑑を欲しがりました。
人体図鑑が誕生日プレゼントって・・・サイコ野郎ではないですよ^^;
科学雑誌のニュートンも、意味はほとんどわかっていないのですが、喜んで読んでいました。
もしかしたら、そこが私の生き物好きの原点であり、観察好きの原点だったのかもしれません。
その後もさりげなくその原点が見え隠れしており、大学も生物系、就職も分析系と繋がっていきました。
幼児と図鑑

さて、我が家には2歳になる男の子がいます。
アリのような小さな虫でも、キャーキャー怖がって、大丈夫かいなと思っていました。
そこで、本棚の目の付く位置に、図鑑を並べてみたのです。
すると、あんなに重たい本をわざわざ引っ張り出し、すぐに神妙な顔をして図鑑に没頭し始めたのです。
もちろん字は読めないし、ページめくりが上手く出来ずにビリビリになってしまうのですが、写真が多いせいか、絵本より断然図鑑に食いつくのです。
怖がらずに興味を持つ
図鑑を読み始めてから、虫を怖がらなくなったのです。
見つけた虫を裏返したり、足を引っ張ったりして観察し(たまに観察失敗でバラけるのですが・・・)、
「このムシ、なにムシだ?」と私に聞いてくるようになりました。
「それは、ダンゴムシだよ」と答えると、
「そっか、ダゴシムか!」と言ってポケットへ(ぷちっ^^;)
これまで黒い塊に恐怖心を抱いていたのが、よく観察することで興味を持ち、探求心や好奇心に変わったのだなと思いました。
幼児の記憶力は計り知れない
読み聞かせていた本を、丸ごと暗唱したり、アニメのセリフを丸暗記していたり、幼児の記憶力って素晴らしいですよね!
最近の図鑑にはDVDがついているものも多く、最初はそんなに必要なのか!?と疑問視していたのですが、これはあった方が良い!!
毎日エンドレスで図鑑DVDを見始めました。
すると、知らないうちに恐竜の名前だったりを暗記しているんですね!
日常で何気なく見かける恐竜のイラストを見ては、
「プレッシャオシャールシュ!(プレシオサウルス)」
「モシャシャールシュ!(モササウルス)」
「ドクリュウとカンナリリュウ(翼竜と雷竜)」
なんて言い出すんですね^^
「図鑑を見えるところに置いておく」。
たったこれだけで、幼児は身の回りの自然科学に興味を持ち、自発的に好奇心旺盛になります。
今では、息子は「虫好き」、「恐竜好き」と周りの皆から思われているようです。
単純に、虫や恐竜に詳しくなるということもありますが、
「知ることで、もっと知りたくなる」
「図鑑で知って、実物にも興味を持つ」
そんな心を育ててくれる、「図鑑」。
ぜひ、子どもたちの周りに置いてみてはいかがでしょうか!
我が家には、2人の幼児がいるのですが、出産祝いやお誕生日などお祝いをいただく機会が幾度かありました。 どのお祝いも心を込めて選んでくださったプレゼント^^ 日々、ありがたく使わせてもらっています♡ 今回はその中でも特に、[…]